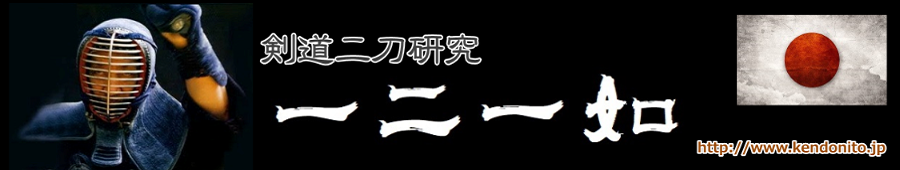二刀の諸規定

二刀も一刀同様に、全日本剣道連盟が定める「剣道試合・審判規則」や「剣道試合・審判細則」等の諸規定がそのまま適用されます。なお、同規則・細則等において二刀に関わる規定等は、以下のとおりです。
![]()
(剣道試合・審判細則)
第2条 規則第3条(竹刀)は、次のとおりとする。
2 竹刀の基準は、表1および表2のとおりとする。ただし、長さは付属品を含む全長であり、重さはつば(鍔)を含まない。太さは、先革先端部最小直径(対辺直径)およびちくとう部直径(竹刀先端より8センチメートルのちくとう対角最小直径)とする。また、竹刀は先端部をちくとうの最も細い部分とし、先端から物打に向かってちくとうが太くなるものとする。
.jpg)
(剣道試合・審判運営要領)
「その他の要領」
1 試合者が二刀を使用する場合は、次の要領で行う。
(1) 小刀および大刀を共に提げ刀する。
(2) 構えるときは、最初に右手で左手に持つ竹刀を抜いて左手に持ち替え、次に右手に持つ竹刀を構える。
(3) 納めるときは、最初に右手に持った竹刀を納め、次に左手に持った竹刀を右手に持ち替え、納める。
(4) その他は一刀の場合の要領に準じて行う。
(剣道試合・審判・運営要領の手引き)
「運用の解説」
二 審判
二刀について
① 小刀での打突が有効打突になるには、大刀で相手の大刀を制している場合で、打った方の肘がよく伸び、充分な打ちで条件を満たしていることを必要要件とする。但し、つば競り合いでの小刀の打突は原則として有効としない。
② 試合中、竹刀が破損し、代えの竹刀がなければ、試合不能として、負けとする。
③ 二刀のつば競り合いは、小刀を下に、大刀を上とし、二刀を交差する形で指導する。
「事例7」
二刀、隻腕、片手上段において、大刀の鍔元(近く)を握ることで小手部を隠すことは反則となるか。
(解説)
1 柄の握り位置は柄頭を原則とするが、柄の握り位置だけをもって判断することは難しいため、防御一辺倒など著しく見苦しい場合は、合議のうえ規則第1条に照らして反則とする。
2 鍔競り合い等の接近した場面で鍔元を握ることは、刀法や間合を考慮し、特に問題としない。