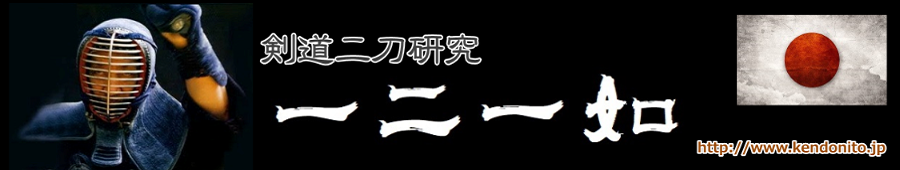二刀の基本技術

「構え」
二刀の構えは、右手に大刀・左手に小刀を持つ「右二刀(正二刀)」と、反対に、右手に小刀・左手に大刀を持つ「左二刀(逆二刀)」とがあり、足の置き方についても、それぞれに「右足前」、「左足前」があります。
二刀の大きな特徴は「片手打ち」であり、その太刀筋にかんがみると、礼法における蹲踞等の際は「中段」となるものの、立合い中は、右二刀でも左二刀でも、大刀を頭上に振りかぶり、小刀の剣先を相手に向ける「上段」の構えをとることが多く、一般的には、「右二刀・上段・右足前」、「右二刀・上段・左足前」、「左二刀・上段・右足前」、「左二刀・上段・左足前」のいずれかの構えが主流となっています。
![]()
「提刀・帯刀」
「剣道試合・審判運営要領」の「その他の要領」1の(1)で定められているとおり、小刀および大刀を共に提げ刀します。両手を自然に提げた「提刀」の状態から「帯刀」の姿勢になる動作は、一刀と同じです。
![]()
「抜刀・納刀」
抜刀は、「剣道試合・審判運営要領」の「その他の要領」1の(2)で定められているとおり、最初に右手で左手に持つ竹刀を抜いて左手に持ち替え、次に右手に持つ竹刀を抜いて構えます。
また、納刀は、同1の(3)で定められているとおり、最初に右手に持った竹刀を納め、次に左手に持った竹刀を右手に持ち替えて納めます。
![]()
「基本打突」
有効打突の条件については、二刀も一刀と何ら変わりありません。よって「剣道試合・審判規則」第12条に定められているとおり、「充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるもの」が有効打突となります。また、打突部位についても、一刀同様に「面」「小手」「胴」「突き」となります。
なお、小刀での有効打突については、「剣道試合・審判・運営要領の手引き」の「運用の解説」二に、「大刀で相手の大刀を制している場合で、打った方の肘がよく伸び、充分な打ちで条件を満たしていることを必要要件とする。但し、つば競り合いでの小刀の打突は原則として有効としない。」と記載されています。
![]()
「つば競り合い」
「剣道試合・審判・運営要領の手引き」の「運用の解説」二に記載されているとおり、「小刀を下に、大刀を上とし、二刀を交差する形」で行います。また、つば競り合いからの小刀での打突については、前述したとおり、原則として有効としないこととされています。